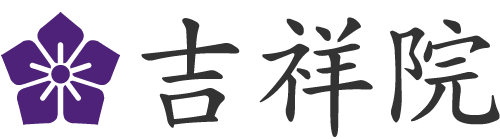仏のことばを読む八. 宝号
南無はインドの言葉そのまま漢字で音写したものです。インドでは今でも挨拶の言葉として頻繁に使われます。日本語の「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」にあたる挨拶はすべてインドでは「ナマステ」と言います。ナマスは「心を傾ける」「従順にいたします」といった意味で、「テ」は「あなたに」という意味となります。この挨拶の語を仏教では帰依の挨拶として取り入れました。
南無本尊界会(かいえ)は本尊とその周囲に集まった菩薩・明王・天などに心からの帰依の挨拶をします、という意味です。界会とは神聖な集会の世界を表します。真言宗の寺院にはさまざまな本尊が祀られます。それがまた真言宗の特徴です。真言宗の教理ではすべての仏の功徳は大日如来にそなわっていると考えられます。そして、大日如来の救いの働きが多くの仏・菩薩・明王・天として現れているのです。それゆえ、どの仏・菩薩・明王・天を礼拝しても、それは大日如来を拝むことになるのです。大日如来を「普門総徳(ふもんそうとく)の本尊」、各寺院に祀られている大日如来以外の本尊は「別徳(べっとく)の本尊」とされます。
南無両部界会の両部とは真言宗の根本経典である『大日経』と『金剛頂経』、そしてこの二つの経典を基にした胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅の世界です。いずれも大日如来(魔訶毘盧遮那如来)(まかびるしゃなにょらい)を中心とするきわめて多くの仏・菩薩・明王・天の集合する世界です。真言宗の寺院では本尊に向かって右側に胎蔵曼荼羅を、左側に金剛界曼荼羅を祀ります。そこに現れているすべての仏や諸尊聖衆(しょそんしょうじゅう)に帰依の心を捧げるのです。
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)はいうまでもなく弘法大師に対する帰依です。大師は偉大な師という意味です。日本では朝廷から下賜される贈り名で、最初に天台宗の最澄上人と円仁上人に、それぞれ伝教(でんきょう)大師と慈覚(じかく)大師の名が贈られました。その後、空海上人にも弘法という大師号が贈られました。次第に弘法大師への信仰が広まると、大師といえば弘法とされ、「お大師さま」と親しみを込めて言われるようになりました。
遍照金剛とはもともとは大日如来の密教の名前です。遍く衆生の世界を照らし、救いをもたらすので遍照といい、金剛は密教における重要な儀式である灌頂の際に授けられたことを表します。弘法大師が中国で恵果阿闍梨について修行をし、師から秘奥を伝えられる伝法灌頂という儀式を受けた時、暗い部屋で目隠しをされて壇に敷かれた曼荼羅に花を投じると、奇しくも金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅と二度も、大日如来のところに花が落ちたと伝えられています。それほど弘法大師は大日如来と深い縁ができたので、遍照金剛という灌頂名を授かりました。すなわち遍照金剛とは、大日如来であるとともに弘法大師でもあるのです。
南無興教(こうぎょう)大師は、真言宗の中興の祖である覚鑁(かくばん)上人への帰依の心を捧げます。興教大師は覚鑁上人に贈られた大師号です。興教大師は平安時代末期に荒廃した高野山を学問の寺院として再興しました。しかし、若くして高野山の座主(ざす)に任ぜられたため、古くから高野山に住していた僧侶たちと緊張関係が生まれました。騒乱を避けるために高野山から退き、新たに根来(ねごろ)に真言宗の学問と祈りの場所をつくりました。それを根来寺といいます。覚鑁上人を慕い、また覚鑁上人の学問を継承する僧侶たちによって、根来寺には多くの修行や学問のための寺院ができました。戦国時代には日本で最大の大学があると、キリシタンの宣教師がローマ法王に報告するほど栄えました。しかし、勢力が大きくなったため豊臣秀吉の軍の攻撃を受け、根来寺の中の一寺院であった智積院(ちしゃくいん)の玄宥僧正が弟子を引き連れて避難し、玄宥の弟子たちが京都に智積院を再興しました。
すなわち、今日の真言宗智山派の源をたどれば覚鑁上人が祖師となります。覚鑁上人は中興の祖として崇拝されるのです。