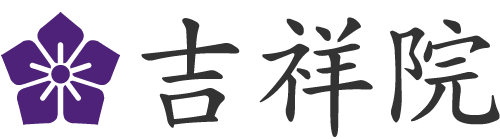仏のことばを読む二. 三帰礼文 その2
 次にもう一つの教えの律についてですが、これも経と同じように成立します。摩訶迦葉が指導した集会で、釈尊が指示した教団生活のきまりを最もよく守り通していた優波離(うばり)がその内容を唱え、それが了承されて釈尊亡き後の教団の生活規則となりました。これを律といいます。ところが釈尊の入滅から時を経てゆくと、地方によって生活環境が異なるために、教団生活の規則についての理解が食い違い、教団が分裂してゆきます。それぞれの教団がそれぞれに釈尊の教えとして律を制定するようになりました。しかし、いずれの教団にとっても、律は釈尊の教えとして伝承され続けました。そのような律の集成を律蔵といいます。
次にもう一つの教えの律についてですが、これも経と同じように成立します。摩訶迦葉が指導した集会で、釈尊が指示した教団生活のきまりを最もよく守り通していた優波離(うばり)がその内容を唱え、それが了承されて釈尊亡き後の教団の生活規則となりました。これを律といいます。ところが釈尊の入滅から時を経てゆくと、地方によって生活環境が異なるために、教団生活の規則についての理解が食い違い、教団が分裂してゆきます。それぞれの教団がそれぞれに釈尊の教えとして律を制定するようになりました。しかし、いずれの教団にとっても、律は釈尊の教えとして伝承され続けました。そのような律の集成を律蔵といいます。その後、経や律の理解に関して食い違いが生じたため、学問僧たちによって経と律を解釈する論という学問書が書かれるようになりました。それぞれの教団は重視する論に基づいて教団の教えを確定するようになりました。この論の集成を論蔵といいます。
ここに経蔵と律蔵に加え、論蔵も成立し、あわせて三蔵というようになりました。中国で三蔵法師という尊称がありますが、それはこの三蔵に精通した学識ある僧侶のことをいいます。『西遊記』で有名な玄奘(げんじょう)も三蔵法師ですが、その他にも有名な三蔵法師がいます。真言宗の重要なお経を中国語に翻訳した不空(ふ くう)という祖師も三蔵法師と崇められました。
三蔵のうち、経蔵と律蔵が仏の教えとしての法で、それはかけがえのない大事なものですから法宝というのです。
次に僧宝とは仏教教団を宝に譬(たと)えたものです。僧とは個人の僧侶を指すのではなく、僧伽(そうぎゃ)という語の短縮した形です。僧伽とは団体を意味する梵語のサンガという語を漢字に音写したもので、元来は教団を意味します。教団では修行僧が協力し修行に励(はげ)むので、その意味をくんでサンガを和合衆(わ ごうしゅう)とも漢字で表記します。僧伽に所属する修行僧は、仏陀の教えに従って自ら修行に励むだけでなく、その教えを弟子に伝え教育する重要な役割を担います。まさしく僧伽がなければ尊い教えも伝えられず、仏教は滅びてしまいます。それゆえ僧伽は仏教徒にとってかけがえのないものなので僧宝といいます。
この僧伽に所属する修行僧は男性と女性に分けられます。男性の修行僧を比丘(びく)、女性の修行僧を比丘尼(びくに)といいます。日本で女性のお坊さんを尼(あま)さんと言いますが、それは比丘尼の「尼」で言い当てているのです。
以上、説明が長くなりましたが、三宝の内容を概説しました。この仏宝・法宝・僧宝の三宝に救いを求めるのが三宝帰依(さんぼう きえ)ということです。
帰依の「依」とは救いの拠り所という意味で、「帰」というのは「行く」という意味です。すなわち帰依とは救いの拠り所に向かって行くという意味です。譬えれば、川の激流に流されてしまったら、川の中にある洲にたどり着けば救われます。その場合に中洲に向かうのが帰依ということになります。苦難の多い人生で救いの場所を求めればそれは三宝になります。人生をしっかり見つめれば、三宝帰依がいかに大事か受けとめることができます。それゆえ三宝帰依をすべての仏教徒が必ず表明します。三宝帰依をしない仏教徒は存在しません。わが国でも仏教が広まり始めた頃に聖徳太子が十七条の憲法で「篤(あつ)く三宝を敬え」と記し、東大寺を造った聖武天皇が「朕(ちん)は三宝の奴なり」と表明したのも、この三宝帰依を仏教信仰の根本に据(す)えたからです。
つづく